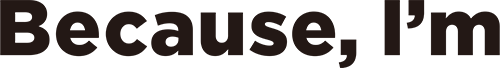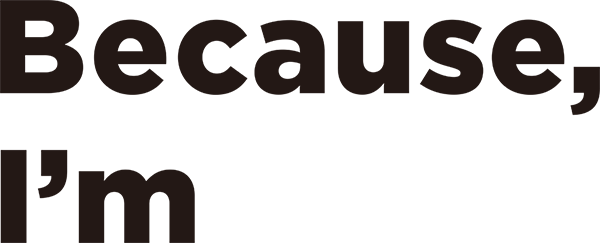

Because, I’m
紋章上繪師 後編
円と線のみで描く家紋デザインの世界。
2014年に日本橋室町にオープンした「コレド室町」。3つの商業施設の入口を飾ったのは、波戸場承龍さんが紋をデザインした大暖簾だ。日本橋は江戸時代の交通路、五街道の中心に位置し、江戸一番の問屋街だったところ。「栄(さかえる)」、「楽(楽しむ)」「桜」という3つのテーマで日本橋の魅力を表現した。さらに企業やイベントのロゴ、イタリアのFURLAのバッグ、ドイツNIESSINGのジュエリー、日本酒のラベルやホテルの空間演出まで、多様なプロダクトデザインにも挑戦している承龍さんと息子の耀次さん。後編では、親子二人三脚で歩んできた日々、その先に見えてきた新たな家紋の可能性を聞いてみた。
Q. 承龍さんから息子の耀次さんへ、ともに同じ道を歩むことになったいきさつを聞かせてください。
承龍 この仕事は僕の代で終わっていいと思っていました。時代の流れの中で着物に家紋を手描きで入れる需要が減り、紋付の紋も印刷することが主流になっている。紋章上繪師の仕事はどんどん減っていたので、息子には「自由に生きていいよ」と言っていたんです。
僕は、厳しい父の元、子どもの頃からレールを敷かれていたので、否が応でも職人にならざるを得なかった。覚悟はしていたから全然迷いもなかったです。手先が器用だったし、数学が好きで、高校の時には計算尺部に入っていました。家紋は対称形なのですべて計算式から成り立っています。曲線もコンパスを何度回転させて描くというのは計算で割り出す。紋の幾何学的な形には数学的な理論が隠されていることが多く、紋の描き方に役立っています。
親父は62歳で引退したので、僕は26歳のときに三代目を継いで、一家の大黒柱になりました。職人としてがむしゃらに働いていたけれど、だんだん仕事の量が少なくなっていく。そこで着物の総合加工業を先輩と一緒に15年ほど続けた後、独立して会社を立ち上げました。仕事も一気に増えたので一人では手が回らなくなり、「ちょっと手伝ってほしい」と息子に声をかけたのです。

互いに同じ道を歩くことになるとは思っていなかったが、家紋デザインへの夢はひとつに繋がった。
耀次 あれは大学1年のときでした。僕はそれまで家業を継ぐことなどまったく考えていなかったんです。大学の専攻は国際政治経済学、全然勉強もしてなかったですけどね(笑)。それでも小さい頃から仕事場で遊んでいたので、家紋はずっと身の回りにありました。父に仕事を手伝ってほしいと言われたとき、初めて自分の将来を考えてみた。あと3年間大学へ通っても、自分の中で本当にやりたいことは見つからないんじゃないかと。それなら早く世に出た方がいいなと思い、大学はやめようと決めたんです。
でも、最初は問屋さんから注文を受けたものを配達するくらいで、アルバイト感覚だった。僕の中でも次世代として受け継ぐ覚悟があったわけではありません。けれど父には、自分にしかできないことをやろうという強い思いがあったようで、50歳になると「後世に何かを残したい。デザインの世界でやっていく!」と僕と母に宣言したんです。

雲をモチーフにした江戸小紋に龍の家紋を合わせ、「雲龍」と名づけたアート作品
Q. 承龍さんが目指したデザインとは、どのようなものだったのですか?
承龍 お客さまから自分だけの紋をデザインして欲しいという依頼があって、オリジナルの紋を作ったらすごく喜ばれたんですよ。猫が好きという女性には猫と牡丹を組み合わせるとか、「孫が生まれたときにプレゼントしたい」という方もいました。11月生まれだから椿の花をモチーフにしたいと言われ、椿の葉を3枚、花びらを5枚、おしべが7つで七五三を見立てた「雪輪に七五三椿」という紋を作りました。
さらに自分でも作品づくりを始めるなかで、どうしたら家紋のデザインが面白くなるだろうと考えた。家紋といえば古臭いとか時代遅れというイメージがあるけれど、もっと恰好良く表現したかったんです。
とはいえ、いきなり「家紋をデザインします」といってもそれだけで食べていけないし、ビジネスモデルもわからない。まずはいろんな人に興味を持ってもらいたいと思い、異業種交流会のような場に顔を出しました。僕らは職人だから営業なんてしたことがないでしょう。とりあえず浅草の古着屋で男物の結城の単衣と野袴を買って、着物姿で営業したら目立つかなと思ったんです。
そんなときネットで見つけたのが、週末に自由が丘で開かれる着物コンテストでした。女性誌の「マリ・クレール」主催で、カジュアルな着こなしを競うというもの。僕が考えたテーマは昔の書生さんです。スタンドカラーの白シャツに青と赤の靴下でトリコロールにまとめ、筒袖にした着物と野袴の裾もきゅっと絞り、ハイカットのブーツを履くというスタイルで出たら、準優勝とダンディ賞をもらったんです。

承龍さんデザインによる、ユナイテッドアローズで販売されたスイカの着物
その参加者の中に「着物で銀座」という会を月一回やっている人がいて、次はそこへ呼ばれました。そこから自分で着物をデザインして作って着て行く事を始めました。7月だったので、麻の着物を作り背中に緑のロープをぐるぐる巻いて蚊取り線香の形に刺繍して、コンバースを履いて行ったんです。すると「波戸場さん、面白いね」と言われ、「来月は何やるの?」と。「じゃあ、お題をもらって着物を作ってくるよ」ということになり、次は「スイカ」の着物を制作。さらに「歌舞伎」というお題が出たときは息子も引っ張り込んで大島紬で黒子の衣装を作り、二人分なので大忙しでした。
そのうち「波戸場さんは職人でモノが売れないだろうから、僕も手伝うよ」という人が現れたんです。彼がユナイテッドアローズに営業してくれて、スイカと蚊取り線香の着物、翌年コンテストで優勝したデニムの着物が商品になったのがスタートですね。着物を着ていろんなところに出ていくと、「あの人、何している人だろう?」と興味をもってもらえる。家紋を描く仕事も知ってもらえるようになりました。

「コレド室町テラス」のイベントで、日本橋の橋の中央にある麒麟像をモチーフにデザインした紋
耀次 父は若い頃から、Yohji Yamamotoが好きでした。だから、僕の名前も「耀次(ようじ)」なんです。デザインにこだわりのある父が作品を生み出すなかで、僕らのターニングポイントになったのがこの工房に越してきた時です。「紋に特化したビジネス、原点に返ろう」と初代の屋号を復活し、2010年に「誂処 京源」を立ち上げました。
この年、ある企業からロゴのデザインを頼まれ、データで納品しなければいけないというので、僕がデータ化を任されました。そこで「Illustrator(イラストレーター)」というグラフィックデザインソフトを買い、トライアル期間に試してみたんです。一か月半ほどで何とか納品することができ、これは家紋との相性がいいと実感しました。
すごく細い線を引くことができ、どんなに拡大縮小しても画像が劣化しない。この先も仕事に使えるんじゃないかと考え、イラストレーターとMacのパソコンを導入したのです。

イラストレーターのソフトを使うことで、大きさも自在に円を描ける楽しさを知った。
実際に使い始めたら、こんなに面白いものがあるのかと思うくらい楽しくなった。僕はこの仕事をするために生まれてきたんだという実感がそこで初めて沸きました。Macとイラストレーターに出合ったことで、すべてがつながったように思えたのです。イラストレーターを使って家紋を表現していけば次世代に継いでいけるものができるのではと。僕もデザインの制作にどんどんのめり込んでいきました。

アトリエではMacを2台並べて、オリジナルの家紋デザインを生み出している。
Q. 昔ながらの技術を受け継いできた承龍さんにとって、デジタルで描くということに違和感はなかったのでしょうか?
承龍 僕は新しいもの好きなので何でも来いという感じ(笑)。息子の隣で見ていたら、Macとイラストレーターがカッコいいから、自分でもやってみたいと思いました。すると家紋はデジタルと相性がいいことがわかって、すっかり楽しくなったんです。
家紋というのは円と線のみで描きます。イラストレーターで表現するときに使うのも、正円ツールと直線ツールだけなんです。僕はもう30年以上、毎日のように分廻し(コンパス)を使って紋を描いていたから、どこに中心点を置いて、どれくらい広げたら思い描く曲線になるというのが身体に沁みついています。デジタルになっても正円ツールを使えば面白いように描けてしまう。そこからは水を得たように世界が広がりました。
さらに手描きでは表すことのない「円と線」の軌跡を、デジタルの画面では可視化することができます。そこであるとき今まで描いてきた円の軌跡を全部残してみたんですよ。すると円が何重にも重なり合って、手描きとはまた違う美しさと広がりを感じさせる独特な世界観が生まれたのです。曼荼羅のように見えたので「紋曼荼羅」と名づけました。
Q. デジタル技術との融合によって、仕事の幅がどんどん広がっていますね。「家紋」をデザインすることで後世に伝えていきたいものは何でしょう。
耀次 手描きの家紋は作品として発表したらそこで終わりますが、僕らがデータ化することでいろんなものを生み出せる仕組みに変わったのです。企業のロゴ制作をはじめ、プロダクトやパッケージのデザイン、空間プロデュースなど、異業種と組むことで多種多様なビジネスモデルが広がっていく。それによって家紋の魅力は海外の人たちからも注目され、世界に日本文化を発信する事業にもつながっています。僕らはこれからも現代のライフスタイルに合わせた家紋デザインを生み出していきたいですね。

銀色や金色で表現した紋曼荼羅を掛け軸にした作品、家紋をはじめ観音像を描いたものもある。


角度を変えると、文字や別のモチーフが浮かび上がる3Dのトリックアートオブジェ
承龍 僕は家紋の魅力を新しい形で表現したいと思い、アート作品を制作してきました。2012年に金魚をテーマにした展覧会「アートアクアリウム」では、金魚鉢に入った土佐金をモチーフにした紋をデザインしました。また日本橋の「コレド室町」にかかる大暖簾では五街道の起点という歴史をふまえ、すべての紋に五の要素を取り入れています。家紋はそれぞれの時代でデザインが異なり、モチーフの構成や変形のパターンがある。それを読み解き、家紋らしさを残しつつ、新しい家紋を作るのが僕らの挑戦であり、面白さでもあります。
現代の生活では家紋との接点が少ないので、「紋切形」のワークショップも始めました。紋切形とは紋章上繪師の仕事から生まれた伝統的な紙切り遊びです。作業の工程には家紋の形をした型紙を彫る作業があります。江戸の人々はこれを応用し、独自の折り方で折った紙をハサミで型通りに切り抜くと美しい紋の形が出来あがるという遊びを楽しみました。今の子どもたちにも遊びを通して、家紋に親しんでもらえたらいいですね。
家紋とは日本独自の文化で、誰もが持つことができるものです。円と線によって構成されたシンプルなデザインには、さまざまな人々の想いや願いが込められている。1000年以上の歳月を経て継承されてきた家紋には、日本人の琴線にふれる美しさがあります。そうした家紋のすばらしさを後世に伝えていきたいのです。

江戸の人々が編み出した紙切り遊び「紋切形」を楽しめる、和紙の折り紙と型紙のセット

家紋のデザインとその歴史や文化を著した『紋の辞典』と、承龍さんが考案した紋描き遊び『誰でもできるコンパスと定規で描く「紋」UWAEMON』の本
(後編 了)
写真 sono
インタビュー 歌代幸子
編集 徳間書店