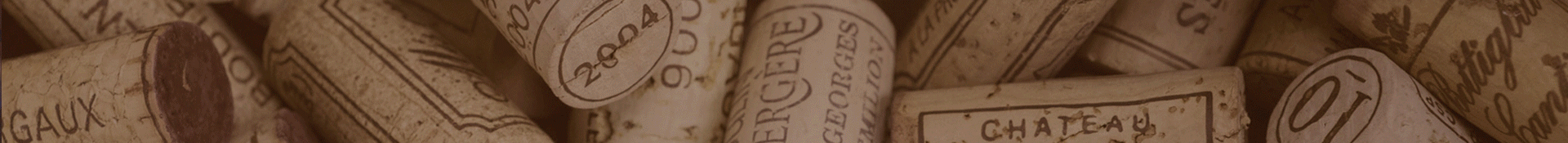Domaine Leroy(ドメーヌ・ルロワ)
この世でただ一つDRCと肩を並べることができるワインがあるとしたら、それはマダム・ルロワのワインである。
目次
歴史
ルロワ家のネゴシアン・ビジネスは1868年、オーセイに拠点を置くワイン商フランソワ・ルロワによって設立された。その後、彼の息子ジョセフと孫息子アンリによって事業規模が拡大した。1942年にはアンリがDRCの所有権の50%を手に入れ、人生の全てを注ぎ込む程の情熱を持ってドメーヌの発展に尽くした。アンリの娘ラルー・ビーズ・ルロワ(マダム・ルロワ)は1955年、23歳という若さで父アンリが営むMaison Leroyに入社した。父はDRCに傾倒していたため家業のネゴシアン・ビジネスに手が回らず、ラルーはゼロから買付の仕事を始めなければならなかった。彼女の定めたルールは極めてシンプルで、「良いものしか買わない」。このスタンスを徹底的に貫いた彼女は、「関係性を保つために〜」、あるいは「付き合いだから〜」といった品質外の観点を一切排除し、毎年同じブドウ農家から自動的に買い付けるようなことを決してしなかった。
1974年、ラルーは父の持つDRCの所有権を引き継ぎ、オーベール・ド・ヴィレーヌとともにDRCの共同ディレクターに選出される。その後1980年、父アンリの死によってラルーはMaison Leroyも引き継ぐことになる。一方で、自らのドメーヌを設立する野心のあった彼女はMaison Leroyの所有権の1/3を高島屋に買い取ってもらうことで資金を調達し、1988年にヴォーヌの名家Domaine Charles Nöellatを購入し、Domaine Leroyを設立した。ここにはRichebourg、Romanee St Vivant、Clos de Vougeot、Vosne Romanne 1er(BeaumontsとBrulees)、Nuits Saint Georges 1er (VignerondesとBoudots)など珠玉の畑が含まれていた。加えて翌年、ジュヴレのDomaine Philippe Remyを買収して規模を拡張した。ここにはClos de la Roche、Latricieres-ChambertinそしてLe Chambertinなどが含まれていた。さらにその一年後、Moine-Hudelot家からLe Musigny、Corton、Volnay1er Santenotsなどの畑を購入する。飛ぶ鳥を落とす勢いのラルーはHospices de Beauneからアンドレ・ポルシュレを引き抜いて醸造責任者としてチームに加え、最強ともいえる体制を築き上げた。
しかし1992年、DRCのワインの販売・流通経路を巡って首脳陣と意見が対立し、ラルーは共同ディレクターを解任されてしまう。さらに1994年にはアンドレとも意見が食い違い、彼は古巣であるHospices de Beauneへ戻ってしまう。それ以来、ルロワのセラーには醸造責任者が不在のままとなっている。
畑
23haの畑を所有する。特級は9つあり、Romanee-St-Vivant(0.99ha)、Richebourg(0.77ha)、Clos de Vougeot(1.9ha)、Le Musigny(0.27ha)、Clos de la Roche(0.66ha)、Latricieres-Chambertin(0.57ha)、Chambertin(0.4ha)、Corton RenardesそしてCorton Charlemagne(0.43ha)という圧倒的なラインナップとなっている。1erは8つあり、Vosne Romanee 1er (BruleesとBeaux Monts)、Nuits St Georges 1er (Vignes RondesとBoudots)、Chambolle Musigny 1er Charmes、Gevrey Chambertin 1er Combottes、Volnay 1er SantenotsそしてSavigny les Beaune 1er Narbantonsである。さらに区画名付きのヴィラージュも8つ持っており、Vosne Romanee Genaivrieres、Nuits St Georges(Lavieres、Aux Allots、Bas de Combe)、Chambolle-Musigny Fremieres、Pommard(Trois Follots、Vignots)、なおAuxey-Duresses Les Lavieresにはシャルドネが植わっている。このほか広域にも畑を所有しており、Bourgogne AligoteやCoteaux Bourguignonsなどをリリースしている。
栽培
ラルーはブルゴーニュにおけるビオディナミのパイオニアとして知られている。故クライヴ・コーツMWによると彼女がビオディナミに開眼したのはNicolas JolyのCoulee de Serrantで、実際にサヴニエールの畑に足を運び手で触って「土が生きている」ことを実感したという。それ以来、彼女は畑でケミカルを一切使用しなくなり、うどんこ病やカビに対する硫黄や銅の散布も極力抑えるようになった。
ラルーの影響力はビオディナミだけにとどまらず、トレサージュと呼ばれるユニークなキャノピー管理にも及んでいる。ルロワではかつて伸びた新梢の先端を短く刈り込むヘッジングが手作業で行われていた。機械だと効率は良いがどうしても荒々しくなってしまうため、時間はかかるがダメージが少ない手作業が取り入れられていたのである。しかし、ラルーはたとえ手作業であってもブドウを切って短くするという行為は自然に反しており、ヘッジングのダメージは今期だけでなく、来期のブドウのパフォーマンスにも影響すると考えた。そこで彼女は先端を切る代わりに束ねて巻き付けるという方法を取った。このトレサージュは副梢の成長を抑えるだけでなく、ダメージがないためブドウ木がより健やかに成長する。同村のシャルル・ラショーやサン・トーバンのオリヴィエ・ラミーといったスター生産者たちはこのアプローチを取り入れその効果を実感している。
そしてなんといってもドメーヌを特徴づけるのが異常な収量の低さである。前提として平均樹齢が高いブドウ木をビオディナミで栽培している畑と若木を慣行農法で育てている畑とでは、前者の収量が低くなるのは当然である。ここからさらにラルーは剪定と収量制限を厳しく課し、ブドウ木1本あたりわずか4房にまで抑えるのである。ジャスパー・モリスMWがラルーに聞いたところによるとドメーヌの平均収量はなんと16hl/haだという。この異常な房数は、通常の房数のブドウ木よりも早く成熟が進むことを意味するが、これがコート・ドールで最も早く収穫を始める生産者の一人であるにも関わらず、未熟感ゼロでフェノールが完璧に熟したブドウの生産を可能にするのである。
醸造
選果は収穫と同じ人数を配置して厳しく行い、その後ブドウは木製の発酵槽へと運ばれる。ルロワは毎年全キュヴェ全房100%を貫くことで知られるが、房をそのまま使用するわけではなく、房から太い主軸(rachis)を一つずつ手作業で取り除いている。この途方もなく手間と時間がかかる作業によってあからさまな茎感がなくなる。この手法は他の生産者(シャルル・ラショーやアルノー・モルテ)にも影響を与えている。キュヴェゾンは21日前後で発酵初期の抽出はルモンタージュ、そこからピジャージュにシフトしていく。プレス後は澱引きせずに樽に移し、マロが終わったらラッキングをする。樽はトロンセ産のオークを使用し、3年乾燥させる。樽メーカーはFrançois Frèresが主だが、一部でCadusも使用している。ラルーはとりわけワインの果実味にこだわるため無駄に長い熟成を嫌っており、特級であっても収穫翌年の12月前後にボトリングするというケースも珍しくなく、一般的なブルゴーニュの常識とはかけ離れていると言える。なお、瓶詰め時の清澄・濾過はもちろん行わない。
味わい
ラルーがこだわるようにルロワのワインは特にフルーツの集中力が異常に高く、全てを飲み込んでしまいかねない濃度を持っている。ところが、味わいはフルーツ一直線という単調なものでは決してなく、八角や五香粉のようなセイボリースパイスとバラや芍薬のようなフローラルさ、オレンジピールのアクセントが多層的に重なり合ってダークチェリーやプラム、チェリーリキュールなどの甘やかな果実に溶け込んでいる。果実の濃度が生み出すテクスチャーのリッチさもルロワの魅力であり、ボディの厚みと相まって口内の隅々まで拡張するような味わいとなる。一方で、熟した滑らかなタンニンとフレッシュな酸が果実を見事に縁取ることで平面ではなく立体的な印象を与えてくれる。長い余韻にはミネラル、お香のようなエキゾチックスパイス、スミレのニュアンスがシームレスに溶け合い、官能的な香り高さが持続する。