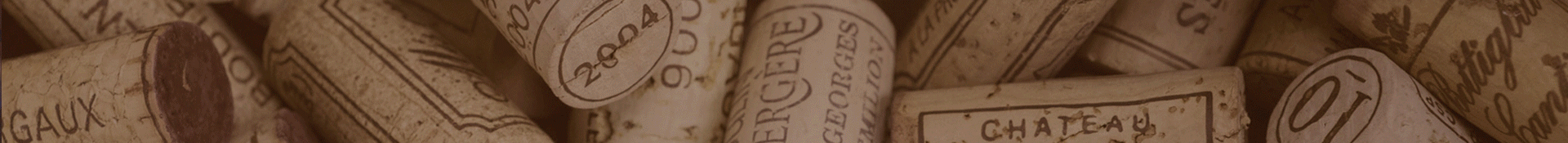Nicolas Joly /Famille Joly(ニコラ・ジョリー/ファミーユ・ジョリー)
今でこそ猫も杓子も声高にビオディナミを謳っているが、ニコラ・ジョリーほど情熱的にこの哲学を語る人間は存在しないだろう。Domaine Leroyのラルー・ビーズ・ルロワにビオディナミを開眼させたのは他でもないニコラ・ジョリーと彼の畑なのである。
目次
歴史
1945年、ロワールのブドウ農家に生まれたニコラ・ジョリーは、大きくなってからすぐに家業を継いだわけではなかった。フランスを出た彼はニューヨークに行くとコロンビア大学でMBAを取得し、その後J.P.モルガンに入社して投資銀行家としてイギリスやアメリカで忙しい日々を送っていた。
しかし、1977年にニコラは金融業界を離れて故郷のロワールに帰ることを決めた。「四年働いた後、ある朝目覚めてもう投資銀行の仕事をしたくないと思った」と彼は語る。故郷に戻ったニコラは家族が所有するCoulée de Serrantという畑を前にして、世界にたった一つしかないこの土地の個性を持つワインを作るという決意をした。そして醸造を学ぶべくボルドー大学に出向いて二年間学んだ。
そんなある日、農業会議所の役人がワイナリーを訪ねてきて、畑の管理方法が古いのでモダンな方法を試してみないかと除草剤を勧めてきた。助言を受け入れて使い始めたニコラは、すぐに後悔することになる。なぜなら使い始めて二年も経たないうちに土の色が変わり、てんとう虫やヤマウズラが畑から姿を消してしまったからである。
この悪影響を目の当たりにした彼は、土地の個性をワインに反映するためには土が生きていなければならないと考えた。ビオディナミの存在を知り、ルドルフ・シュタイナーの哲学に深く感銘を受けた彼は、このコンセプトを畑で実践し始めた。こうして1980年代という早い時期からビオディナミを取り入れ、1984年には全畑を転換した。
しかし当初、周りの反応は冷ややかだった。両親のもとには「ニコラが畑を壊している」とよく電話がかかってきて、カルト的な扱いを受けることも少なくなかった。しかし、ラルー・ビーズ・ルロワがビオディナミの教えを請いにやってきてから周囲の対応が変わったとニコラは言う。それ以降、彼はビオディナミの提唱者として数え切れないほど多くのヴィニュロンたちにレクチャーを行い、その哲学を広めていった。
2015年、業界を騒がせるニュースが報道された。法廷で所属団体Interloireへの未払い会費(約5,800 euro)を支払うように命じられたニコラがこれを拒否し、団体からの撤退を宣言したのである。彼は未払いの理由を、Interloireがメンバーから徴収している会費をオーガニックやビオディナミ生産者たちではなく、テロワールを無視した工業的な大規模ワイナリーのプロモーションに使用しているからだと主張した。Interloireから撤退することを決めたジョリーは、自身でRenaissance des Appellations(return to terroir)という団体を立ち上げた。ここには世界の各国から200名を越すメンバーが所属しており、自然派のスター生産者が多く名を連ねる。
現在ワイン造りを行うのはニコラの娘ヴィルジニー。もともと家業を継ぐ予定ではなかったが、2002年にワイナリーに戻ると徐々にニコラの仕事に加わるようになっていった。2016年からはニコラの息子ヴァンサンも加わり、ニコラの哲学は着実に新しい世代へと受け継がれている。
畑
サヴニエールに15haの畑を所有する。畑は3つに分かれており、土壌は全てシストとなる。フラッグシップはモノポールのCoulée de Serrant(7ha)で、ここは単独でAOCを名乗ることが許されている特殊な畑である。DRCのRomanee ContiやLa Tache、北ローヌのChateau Grilletがそうであるように、単独の生産者がアペラシオンを丸ごと所有するという極めて珍しいケースにあたる。日当たりの良い南向きの急斜面を持ち、表土は薄く20cmにも満たない。続いてClos de la Bergerie(3.2ha)はすぐ隣のAOC Roche aux Moinesにある。東向きの緩やかな斜面を持ち、Coulée de Serrantと似た土壌を持つが表土は60-70cmと厚さが増す。そして最後はLes Vieux Clos(5ha)となる。サヴニエール内に位置するこの畑は東向きの急斜面を持ち、表土が1.5mと非常に厚く、さらに砂が多く混ざっている。
栽培
1980年代の初期に、従来の慣行農法とは全く異なるビオディナミを取り入れたニコラは、著名なワインライターであるジェイミー・グッドに「化学肥料は塩と同じです」と語った。植物は塩辛さを薄めるために水を欲しがるようになり、この水分過多はどんどん成長を促進する。この勢いは夏至を過ぎても止まらず、本来起こるべき種と果実の成長に悪影響を及ぼす。このアンバランスな状態が結果として腐敗を引き起こすと、今度は腐敗を抑えるために別のケミカルに頼ることになる。こうして負のスパイラルが完成する。
化学肥料とケミカルを拒むニコラのドメーヌでは自社畑に生息するハーブから作った調剤を撒き、月のサイクルに従って作業を行う。またモノカルチャーは自然の最大の敵だと信じるニコラは、エコシステムを活性化させるためにロバ、ヤギ、羊など多様な動物を放し飼いにしている。「ブドウは春から秋にかけて小さな芽からhaあたり数トンのもの物質に変わるわけです。しかも毎年のように。その94%は光合成によるものです。これを深く理解すれば生命というのは地球ありきではないことに気づきます。太陽系の一員であるからこそ我々は生を受けるのです。」
醸造
「栽培をしっかりやっていればセラーですることは何もない」というニコラは、セラーでワインをコントロールするという考えに異論を唱える。収穫は区画ごとに別々のタイミングで行うが、毎回畑を何度も往復して熟度を厳しくチェックする。こうして得た完熟ブドウを空気圧式でプレスし、そのまま500Lの古樽へと移していく。天然酵母にこだわるジョリーは培養酵母の使用をナンセンスだと指摘する。「ある年の機微、その全ては天然酵母に記録されますが、培養酵母はこれを殺してしまう。」つまり培養酵母はその年のエッセンスを無慈悲にも消し去ってしまうのである。
ビオディナミを実践する生産者の中には培養酵母だけでなくSO2も拒む者たちが少なからず存在する。意外に思えるかもしれないが、ニコラは正しい種類のSO2の使用に好意的である。原料が大きな違いを生むと考えている彼は、自然のもの、つまり火山から放出されるSO2を好む。硫黄を燃やすことによって発生させたものであれば問題ないが、SO2を液体としてワインに加えるべきではないと言う。「SO2はワインを遠くへ運ぶ際のベストな保護者です。ですが、直接燃やして発生したものでなければなりません。」
味わい
「サヴニエールは鋭く厳格でなければならないと考える人がいますが、私は反対です」というニコラの言葉が表す通り、彼のワインは大きくパワフルでほとんど快楽主義的だと言っても良いだろう。ボトリティスがついたブドウを使うことを全く恐れておらず、15%近くまでアルコール度数が上がることも珍しくない。さらにマロラクティック発酵による柔らかなテクスチャーも相まって同じシュナンでも内陸のヴーヴレイとはスタイルが全く異なる。だからといってそのパワーと重さを支えるものがないのでは、と心配する必要はない。むしろ逆である。シスト由来の図太い鋼のミネラルとシュナンの突き抜ける強烈な酸が芳醇でリッチなフレーバーを見事にバックアップしている。一口飲めばリッチさを上回るスケールの大きさに圧倒される。また年によってクリーンか酸化的かといったスタイルに幅があるのもニコラのワインの特徴である。酸化的なニュアンスとしてはシードルやりんごの皮、あるいは切ってから時間がたったりんごにみられるアセトアルデヒド的なほろ苦さがあり、ナッツや土っぽさが果実のピュアさをやや覆い隠すような味わいとなる。一方でクリーンな年はフローラルではちみつ漬けの花梨、アプリコットや桃の甘みを感じ、エキゾチックスパイスとフリント、そしてはっきりとした塩味がフィニッシュまで持続する。
-
前の記事

Huet(ユエ)
-
次の記事
記事がありません