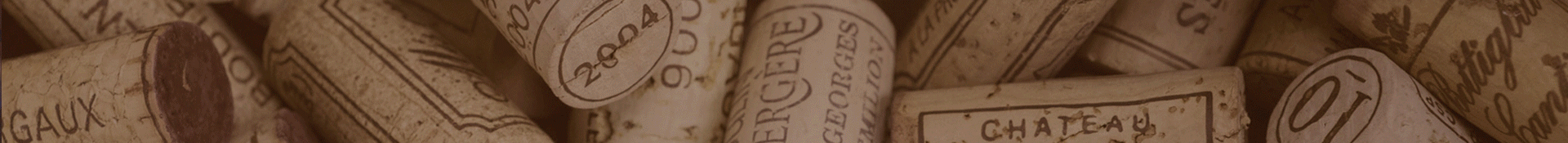Zind Humbrecht(オリヴィエ・フンブレヒト)
オリヴィエ・フンブレヒトは世界でもごく僅かなワインメーカーのMWであるだけでなく、ビオディナミ認証団体Biodyvin設立に携わり、プレジデントを務めた人物としても知られている。
目次
歴史
フンブレヒト家のブドウ栽培の歴史は1620年にまで遡ることができる。現ドメーヌ設立のきっかけは1959年、レオナルド・フンブレヒトとジュヌヴィエーヴ・ツィントの結婚である。両家の畑が統合されドメーヌ・ツィント・フンブレヒトが誕生した。当初はわずか4haの規模だったが、レオナルドは徐々に畑を買い増していき、1977年にBrandやRangenのClos Saint-Urbainを手に入れた。当時のアルザスでは、畑仕事はトラクターに任せという効率重視の考え方が常識だったため、みな平坦な畑を買いたがった。ランゲンのような目も眩む急斜面の畑を欲しがるのはレオナルド以外におらず、周囲の農家はなぜ手作業を強いる面倒な畑をわざわざ買うのか理解できなかった。しかし、1983年アルザスにグラン・クリュシステムが導入された際、ランゲンは真っ先に特級畑に認定された。レオナルドはその後もClos Jebsal、Heimbourg、Clos Windsbuhlなどを取得し、どんどん規模を拡大していった。
1989年、レオナルドとジュヌヴィエーヴが引退となり、息子オリヴィエが当主となった。同年、オリヴィエは26歳という若さでフランス人初のMWとなった。彼は1990年代後半からオーガニック栽培を取り入れるようになり、1999年までに全ての畑をビオディナミに転換した。
2019年からはオリヴィエの息子ピエール・エミールがワイナリーに加わった。彼のインターンシップ先はスイスのMarie-Thérèse Chappaz、ジュラのStephane Tissot、そしてDRCと一流の生産者ばかりであり、ドメーヌの次世代を担う彼の活躍に期待が高まる。
畑
約40haの畑を持つ。畑の約半分はワイナリーのあるTurckheimにあり、残りは複数の村(Hunawihr、 Thann、Gueberschwihr、Wintzenheim)にまたがる。多数のモノポール(Clos Windsbuhl, Clos Hauserer and Clos Jebsal)に加えて、4つのグラン・クリュを所有する。Clos Saint-Urbainで知られるRangen(5.5 ha)は火山岩と堆積岩(砂岩)からなる土壌を持ち、スモーキーでフリンティなミネラルが特徴となる。Brand(2.4 ha)はTurckheim花崗岩と呼ばれる土壌を持つ。Hengst(1.4 ha)は南東向きの急斜面で、石灰岩とマールに一部花崗岩、砂岩、シリカを含む小石からなる。Goldert(0.9 ha)はアルザスでは珍しい魚卵状石灰岩を下層土に持ち、表層部は粘土と砂岩からなる。
ブドウ品種はリースリング、ピノ・グリ、ゲヴュルツトラミネールが90%を占めている。残りはPinot Blanc、Muscatに加えClos Winsbuhlの一部に少量のChardonnayとAuxerroisが植わっている。
栽培
オリヴィエの時代にワイナリーは大きく飛躍するが、当初畑の状態は決して良いものとは言えなかった。それまで大量に使っていた肥料のせいで畑の土が疲弊していたのである。マグネシウム、カリウム、ホウ素などが欠乏しており、石灰岩土壌であるにも関わらず、カルシウム不足の症状がでる畑もあった。加えて90年代初期には害虫被害もあり、オリヴィエはブドウの品質に満足していなかった。そこで近隣の農家から牛糞を仕入れて堆肥を自作するようになった。しかし当初は効果を実感できず、農家にどんな餌を与えているかを聞き、その成分表を薬剤師に見せにいった。その結果、餌が抗生物質や薬剤にまみれていたことが判明した。大量の抗生物質を摂取した牛の体から排出される糞は不自然そのものであり、地中のバクテリアはこれをうまく分解することができなかったのである。オリヴィエは良質な牛糞を模索する中であるオーガニック農家と出会った。その牛糞で堆肥を作ったところ土への効果は抜群で、詳しく話を聞くと彼らがビオディナミを実践していることを知った。それがきっかけとなり1996年からは自分自身でビオディナミの堆肥を作り始め、1999年までに全ての畑をビオディナミに転換した。それ以降、健全な土による健全なブドウはオリヴィエのワインの品質を大きく向上させた。
醸造
オリヴィエの父レオナルドは、当時技術的に最先端を行くワインメーカーであり、アルザスにおけるイノベーターでもあった。1981年という早期に樽発酵の温度管理・冷却システムを取り入れ、1986年には空気圧式プレスを導入した。このおかげで全房プレスが可能となり質の高い果汁が取れるようになった。偉大な父を持つオリヴィエはハンズ・オフのアプローチでブドウのポテンシャルをさらに引き出すことに成功した。「ワインが望むようにさせる」ことをモットーとする彼は、ワインを大きな古樽で発酵させる。介入をしないため自然酵母が活動を開始したら発酵が始まり、死滅したら発酵が終わる。なので発酵は数週間で終わることもあれば一年以上続くこともある。ワインの甘さも狙いを定めて途中で発酵を止めるのではなく、あくまでもワインに決めさせる。基本的にラッキングはせず最大24ヶ月もの間澱とともに熟成させる。この澱との長期熟成とマロを完全に行うのでワインの安定性が上がり、SO2を最小限に抑えることができる。瓶詰め前に軽くフィルターを通すが、これはもちろんオリヴィエの本意ではない。多くのワインで豊富な残糖がみられるため、ノンフィルターだと再発酵のリスクが高くこれを避けるための苦肉の策だという。「濁ったワインをフィルターに通すとワインを傷つける」というオリヴィエは、樽内でワインがきれいに清澄したのを確認してからフィルターに通すことを徹底している。
味わい
一昔前はリッチでフルボディ、凝縮したエキゾチックなフレーバーがフンブレヒトのスタイルであり、地球温暖化以前の時代において、あの深みと濃度は傑出した個性であった。しかしここ数十年でスタイルは変わり、現在ワインメイキングの舵を取るピエール・エミールはエレガンスとニュアンスに富んだ味わいを追求している。例えばリースリングのClos Saint Urbainのアルコールと残糖を例に取ってみると1998年は13.99%で34g/L、2000年は14.3%で19g/L、2002年は14.7%で25g/Lである一方、2018年は13.4%で残糖2.7g、2019年は13.2%で2.8g、2020年は13.6%で5.5g/L、そして2022年ではアルコール度数が13%以下となっている。しかしだからといってフンブレヒトらしさがなくなったというわけではなく、完熟したアプリコットやピーチ、蜂蜜のフレーバーが作る素晴らしい濃度と凝縮感は顕在である。そこに近年のレーザーのようなシャープさが加わり、砕いた岩、塩味、フリント、スモーキーなミネラルが活力と張りを与えている。リッチさとエネルギーの絶妙なバランスにアルザスらしいフェノールのグリップ感と強固なストラクチャーが調和することで驚くほどに長い余韻につながり、向こう数十年にわたって進化し続ける熟成能力を示す。
-
前の記事

Weinbach(ヴァインバック)
-
次の記事
記事がありません