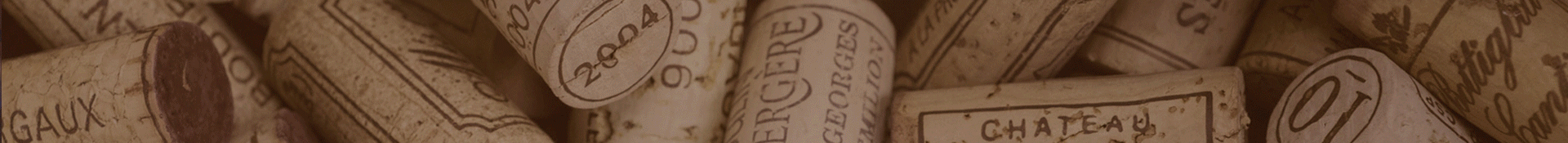Lecheneaut(レシュノー)
ワインの世界には知名度やキャッチーなストーリーが先行して品質は二の次という作り手が少なからず存在する。一方で、誰もが知るスターではないものの一貫した品質を持ち、飲み手の期待を決して裏切らない職人的な作り手もひっそりと存在する。後者の代表格と言えるのがニュイ・サン・ジョルジュのレシュノーである。
目次
歴史
ドメーヌは1950年代フェルナン・レシュノーによって設立された。もともとニュイに拠点を置くMaison Morin(ネゴシアン)で働いていた彼は、ニュイ・サン・ジョルジュ、モレ・サン・ドニ、シャンボール・ミュジニーに小規模の畑(2.5ha)を所有しており、これがドメーヌの基盤となった。設立当初は作ったワイン全量をバルクでネゴシアンに販売していた。ワイナリーの規模と評判が一気に高まったのはフェルナンの息子フィリップとヴァンサン兄弟に代替わりした1985年からである。彼らはすぐにニュイ・サン・ジョルジュやヴォーヌ・ロマネに畑を買い足し、自社瓶詰めを始めた。今日では12haの畑から20を超える幅広いラインナップを生産している。なお、現在はドメーヌを支えてきたフィリップ(兄)の引退に伴ってヴァンサン(弟)の息子ジュールがワイナリーに参画している。
畑
12haの畑を所有する。特級は雀の涙ほどのClos de la Roche(0.09ha)で、斜面上部にありDujacの区画に隣接している。ニュイ・サン・ジョルジュの1erはPruliers (0.51ha)とLes Damodes (0.55ha)がある。後者は一級と村名の両区画を所有しており、昔はブレンドして村名格としてリリースしていたが、現在は1erを分けて瓶詰めしている。余った村名区画分はノーマルのヴィラージュにブレンドされている。また近年新しく1er Aux Argillatsがリリースされるようになった。シャンボールの 1er もLes Damodesと同じで、以前はLes PlantesとLes Borniquesをブレンドして区画名の付かない1erとしてリリースしていたが、2019年からLes Borniquesを分けて生産するようになった。余ったLes Plantesは贅沢にもノーマルのヴィラージュにブレンドされている。モレにも少量の畑 1er Charrieres(0.1ha)を持ち、また近年新しくAloxe Corton からも1er Les Petites Lolieresが加わった。
区画名付きの村名はNuits St Georges Au Chouillet (0.72ha)とMorey St Denis Clos des Ormes(0.15ha)を持っており、後者は 1erのブドウも多く使っているが、ヴィラージュも混ぜて醸造しているため村名としてリリースされる。ノーマルのヴィラージュはNuits St Georges (1.45ha)、Morey St Denis (0.94ha)、Gevrey Chambertin (0.47ha)、Chambolle Musigny (0.42ha)、Vosne Romanee (0.42ha)、Marsannay (0.27ha)とコート・ド・ニュイの主要産地を網羅しており、さらにコート・ド・ボーヌにもChorey les Beaune (0.51ha)を持つ。広域はHautes-Côtes de Nuits Rouge (1.2ha)、Côtes de Nuits Villages Le Clos de Magny (0.4ha)、そしてBourgogne Rouge (1ha)となる。
生産量は少ないが一部で白ワインも作っており、Morey St Denis Pierre Virant (0.17ha)に加え、Hautes-Côtes de Nuits Blanc (0.34ha)とAligote (0.25ha)を生産している。
栽培
レシュノーでは2000年からオーガニック栽培を取り入れ始め、徐々に規模を広げていき2021-2022年にかけて全面転換した。ヴァンサンの息子ジュールは近年、一部でビオディナミを実験的に取り入れている。収量制限は芽かきを中心に行い、シーズン中に予想収量を遥かに上回る場合はグリーンハーヴェストで調整する。
醸造
収穫時に最初の選果を行った後、ワイナリーで二度目の選果が厳しく行われる。レシュノーは基本的に除梗するスタイルだが、状況によっては全房を使用する場合もあり、例えば温暖な年はフレッシュさを保持するために最大50%まで使用することもある。発酵の前に数日間の低温浸漬を行い、約3週間のキュヴェゾンが続く。近年では以前と比べてピジャージュの回数が減り、抽出がより穏やかになった。また新樽率も1/3程度と控えめになった。ワインは18ヶ月の樽熟成後、タンクで落ち着かせてから無濾過・無清澄で瓶詰めされる。
味わい
かつてのレシュノーは樽感と抽出がやや強く出るスタイルだったが、現在はより上品なスタイルにシフトしている。抽出が穏やかになり新樽率も下がったことによって、重さや濃さといったインパクトではなく、心地よい濃度とテロワールの個性が楽しめる洗練された味筋となった。どのキュヴェにも一貫していえるのはベリー系の甘やかさと土やスパイス由来のセイボリーさの見事なバランスである。ラズベリーやチェリーの赤系に加えてブラックベリーなどのダークフルーツも感じられ、そこにリコリスやクローヴなどのウォームスパイスが複雑さを与えている。チョーキーなタンニンと生き生きした酸が贅肉のない筋肉質な骨格を作り、砕いた岩のようなミネラルが余韻までしっかりと続く。上級に行くにつれて口内に張りが出るようなり、同時に深みのある果実味がコアに感じられる。特級や1erが素晴らしいのは無論だが、このドメーヌの魅力が一番に感じられるのはヴィラージュクラスのワインたちではなかろうか。その理由は(1)スター生産者たちよりも遥かにリーズナブルな価格であり、(2)ワインメイキングの影響が強くですぎておらず、(3)畑の微妙なニュアンスが正確に表現されているからである。実際にステファン・タンザーはVinousでレシュノーのヴィラージュワイン(ジュヴレ、モレ、シャンボール、ヴォーヌ、ニュイ)をブルゴーニュ・マスター・クラスのパーフェクトな教材だと語っている。ワイン・スノッブたちが飛びつくような特級や1erではなくスタンダードなヴィラージュにこそ職人技を光らせるレシュノーは、飲み手を裏切ることなくブルゴーニュの魅力を教えてくれる。
一方、レシュノーは幅広いAOCからワインを生産しているため、飲み手からするとどの村の造り手なのかはっきりとしないというイメージの弱さがある。これが良いワインを造っているにも関わらず人気が爆発しない理由の一つでもあり、この「知る人ぞ知る」的な立ち位置が価格をリーズナブルに保たせている。