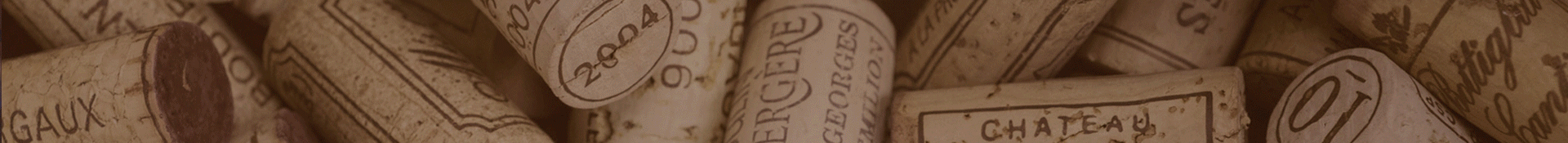Domaine de la Romanee Conti(ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ)
ブルゴーニュを愛する我々にとってDRCほど刺激的なドメーヌは他にないだろう。9つの特級畑から世界最高峰のワインを生み出すこのドメーヌは、何十年もの間ブルゴーニュの、いや世界の頂点に君臨し続けている。
目次
歴史
DRCは1869年にRomanee Contiの畑を購入したジャック=マリー・デュヴォー・ブロシェの後継者であるド・ヴィレーヌ家が長らく所有していたが、1942年に同家の一人が所有権(50%)をアンリ・ルロワに売却し、ルロワ家との共同所有となった。アンリ・ルロワは1954年にこの権利を二人の娘に受け継ぐが、そのうちの一人がマダム・ルロワとして知られるラルー・ビーズ・ルロワである。その後1974年にド・ヴィレーヌ家のオーベールとルロワ家のラルーはDRCの共同ディレクターに選出される。二人はすぐに当時ブルゴーニュでは珍しかった選果台を導入してブドウの品質を厳しく管理し、新樽率もそれまでの50%から100%へと大きく変化させた。一方畑でもラルーの情熱的な取り組みによってDRCの畑はオーガニックに転換し、ブドウの品質はさらに高まった。しかしながら、彼女は皆に好かれるタイプではなく、時として彼女の意見は大きな対立を生むこともあった。その結果、ラルーは1991年に共同ディレクターを解任されることとなった。後任はラルーの甥シャルル・ロックが選ばれたが、就任して三ヶ月も経たないうちに彼は交通事故で命を落としてしまう。翌1992年、弟のアンリ・フレデリックがシャルルの跡を継いで共同ディレクターの座に付き、オーベールと二人三脚が始まった。
それから時は流れ、DRCには再び大きな変化が訪れる。まずは2018年のベルナール・ノブレの引退である。ノブレ家とDRCは切っても切れない関係にあり、1946年に醸造責任者に就任したアンドレ・ノブレに始まり、1978年に息子ベルナールへと引き継がれてから40年にもわたってDRCの醸造を支えてきた。ベルナールの引退に伴って後任に選ばれたのはベルナールの下で8年間ワイン造りを学んだアレクサンドル・ベルニエである。
続いて同年、共同ディレクターであるアンリ・フレデリックの逝去である。彼の後任はラルーの娘ペリーヌ・フェナルが選ばれた。
そして2022年、半世紀近くもの間DRCの顔で有り続けたオーベール・ド・ヴィレーヌの引退発表である。現在は彼の甥ベルトランがその座を引き継ぎ、ルロワ家のペリーヌとともに新共同ディレクターとしてDRCの舵を取っている。
畑
28haの畑を所有している。ヴォーヌ・ロマネ(フラジェ・エシェゾーを含む)に6つの特級畑を持ち、2つのモノポールRomanee Conti(1.81ha)とLa Tache(6.06ha)を筆頭にRichebourg(3.51ha)、Romanee-St-Vivant(5.29ha)、Grands Echezeaux(3.53ha)、Echezeaux(4.67ha)と続く。なおDRCはそれぞれの畑の最大の所有者でもある。畑は特級だけでなく1er のPetits MontsやLes Gaudichotsも所有している。これらは特級の若木とブレンドしてVosne-Romanee 1er Cru Duvault-Blochetとしてリリースされていたが、2018年よりPetits Montsは分けて瓶詰めされ仏国内のレストランに向けて販売されるようになった。また、2009年からはCortonも作っている。Prince Florent de Merodeからの借り畑で、Les Bressandes(1.2ha)、Le Clos du Roi(0.57ha)、Les Renardes(0.5ha)がブレンドされている。
一方、白ワインはシャサーニュ側に位置するLe Montrachet(0.68ha)とCorton Charlemagne(2.49ha)である。後者はBonneau du Martrayからの借り畑で2019年がファーストヴィンテージとなる。区画は6つありEn Charlemagne (Pernand-Vergelesses)とLe Charlemagne (Aloxe-Corton)にまたがる。また公にリリースされていないが、ドメーヌのプライベート消費用にBatard-Montrachet(0.17ha)が生産されている。加えてレアワインとして知られる年産わずか数千本のHautes Cotes de Nuitsもある。これはオーベール・ド・ヴィレーヌとサン・ヴィヴァン修道院協会が所有する畑(シャルドネ)をDRCが醸造しているというもの。ワインの売上はヴォーヌ・ロマネから約10km西に位置するCurtil-Vergy村にあるサン・ヴィヴァン修道院の修復費にあてられている。
栽培
DRCでは1985年という早い時期にオーガニック栽培に転換し、1990年代後期にはビオディナミのファーストトライアルを行った。そこからすぐにビオディナミに転換するわけではなく、じっくりとその哲学を受け入れていき、2007年に栽培責任者ニコラ・ヤコブのもとで全面転換した。
DRCの品質とスタイルはいくつかの畑の要素に依存している。まず全畑において見られる50年という高い平均樹齢である。次に植樹にはRomanee ContiやLa Tacheからマッサル・セレクションで選び抜かれた最上の苗木が用いられ、収量の低い凝縮したブドウが手に入ることが挙げられる。さらに作業人数の多さもDRCの強みであり、故クライヴ・コーツMWによると畑では25名の正社員がそれぞれ1haずつブドウの面倒を見ており、収穫時にはさらに人が加わって60名を超えるチームとなり、全畑の収穫を8日で終わらせることができるという。注意深い観察と選果によって基準に満たないブドウは容赦なく弾かれ、最高級のブドウのみが残される。そして最後にDRCのスタイルを特徴づける遅い収穫である。ドメーヌの祖先ジャック=マリー・デュヴォー・ブロシェは熟度を担保するために遅摘みを提唱していたが、その哲学は今日の子孫たちにしっかりと継承されている、とジャスパー・モリスMWは指摘している。かつては周囲が収穫を始めてから少なくとも一週間たってから開始というのがDRCの通例であった。しかし、近年は気候変動の影響により状況によっては収穫を早めるケースもでてきている。また熱対策として、収穫したブドウを低い温度で保つ冷却装置を導入したり、収穫の時間帯を朝6時から午後2時までに限定するなど柔軟に対応している。
醸造
オーベール・ド・ヴィレーヌはかつて「茎は骨であり、果実は肉体である」と言った。この言葉に裏付けられているようにDRCでは長い間全房が積極的に使用されてきた。しかし全て100%全房で仕込むLeroyと違ってDRCでは年によってその比率が変わる。温かい年は100%になる傾向があるが、70-90%というのが通例となっている。
セラーに到着したブドウは厳しく選果され、大きな木製発酵槽に運び込まれる。まずは15℃程まで冷やして、ゆっくりと低温浸漬をスタートさせる。その後天然酵母による発酵が始まると温度はピーク時で35℃近くまで上がる。抽出は発酵初期にルモンタージュを、後期にはピジャージュにシフトしてく。18-21日前後のマセラシオンが終わったらプレスを経て大きな澱を取り除いてから新樽(100%)に移される。オーク材はTronçais産とBertranges産で、樽会社はFrançois Frèresが主体となっており、これに加えて近年赤ではLe Grangeの樽が、白ではSeguin Morey、Damy、Taransaudの樽が一部で使用されるようになった。ワインは樽で二冬過ごした後、タンクに移してブレンドし月のサイクルに従って瓶詰め。清澄とろ過は行わない。
味わい
例えば全房100%かつ新樽100%であるにもかかわらず、どちらの要素もほとんど目立たないワインがあるとしたら、それは果皮が厚く、重いボディを持ち、過熟なフレーバーで覆い尽くされた濃いワインだろうか。それと対極にあるような果皮が薄く、繊細なアロマとエレガントなフレーバーを持つブドウでは当然太刀打ちできず、ましてやわずかな畑の位置や微妙な天候の違いを忠実に映し出すピノ・ノワールではまずありえない、と思うだろうか。この常識を見事に打ち砕いてくれるのがDRCである。もちろん、オークの香ばしさや茎がもたらすウッディー/ボタニカルなノートはヴィンテージやキュヴェによって特徴的に現れてくることもある。しかし、それらが全体を制圧することは決してない。それは古樹×低収量×完熟ブドウがもたらすフレーバーのインテンシティと凝縮感が見事にバランスを取っているからである。
単純な果実味の強さや艶感だけでいえばDomaine Leroyに軍配が上がるだろうが、DRCの魅力は凝縮感があるのに重さを感じさせない「抑制」にあるといえる。この抑制された枠内において、ザクロのような透明感、レッドカラントのリキュール、ときには黒糖のような濃密な甘やかさ、セイボリーな大地香、アニスのようなスパイス、フローラルな芍薬、オレンジピールのノートがシームレスに調和し、エレガンスとフィネスを生み出している。また存在を忘れるぐらい見事に溶け込んだタンニンの質感はシルクそのもので、フレッシュな酸とともに余韻までしっかりと張りを与えてくる。
-
前の記事

Arlaud(アルロー)
-
次の記事
記事がありません