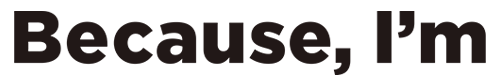ワインのある景色―10月 (18)
- 2025.10.01
- ワインのある景色

シャブリのお話。フランス・ブルゴーニュ地方最北端で造られるこの白ワインの名前を、私はワインのいろはを学ぶ前から知っていました。ワインショップの棚やレストランのワインリストにはシャブリという文字を大抵は見つけることができ、辛口の白ワインが飲みたい時はシャブリを選べば間違いないと思っていました。ワインを知らない私でも名前だけは知っていたのは、それだけ有名で日本市場に多く出回っていたからなのですが、ワインを学ぶにつれて他にも美味しい白ワインがたくさんあることを知り、徐々にシャブリを選ぶことが少なくなっていきました。「シャブリなんて」と軽んじていたこともありました。
Fête des Vins de Chablis(シャブリワイン祭り)
再びシャブリに目が向くようなったのは、毎年10月第4週末にシャブリ地区で開催される「 Fête des Vins de Chablis(シャブリワイン祭り)」を訪れたのがきっかけでした。普段は静かなシャブリ村が大勢の人で賑わうこのお祭りは70年以上の歴史があり、ブドウ畑ツアーあり、マラソン大会あり、オリジナルのワイングラスを購入すると様々な生産者の様々な等級のシャブリを無料でテイスティングすることができる一大イベント。
なだらかな丘陵地帯に広がるシャブリ村には300軒以上のドメーヌと呼ばれる自社畑のブドウでワインを造っている生産者の他に、協同組合や購入したブドウでワインを造るネゴシアンなど数多くの生産者が存在し、シャルドネ種単一で造られているのにその味わいの多様なこと。なかなか面白いと気付かされました。
年間約4,000万本近く造られる内の70%以上は輸出されており、最も多く輸出されているイギリスに続いて、米国、カナダ、そして日本が第4位に君臨しています。様々な国のワインが日本に輸入されるようになった現在でもシャブリが多く消費されているのは、やはり「和食との相性が良いワイン」という不動の地位にあるからでしょう。
牡蠣にはシャブリ
どのワインにも共通するのは少し塩味を感じる豊かなミネラルと爽やかな酸。これは約1億5千年前のジュラ紀、まだこの地区が海だった頃の貝殻の化石を多く含んでいるキンメリジャンというシャブリ特有の石灰質土壌に由来しています。よく「牡蠣にはシャブリ」といわれますが、それはこの貝殻混じりの土壌がもたらす味わい所以なのです。
お祭りにはもちろんフランス人の大好物(私も!)、生牡蠣の屋台も出ています。シャブリを片手に、みんな次から次へと生牡蠣をチュルッと口に運びます。ひとり1ダースはほんの序の口です。
今まさに旬を迎えている生牡蠣ですが、フランスの生牡蠣の養殖には日本が大きく貢献したということは知る人ぞ知る有名なお話。1960年代、当時フランスの養殖牡蠣の主流だったヨーロッパ・ヒラガキに病気が蔓延して絶滅の危機に瀕し、それを救ったのが日本の宮城県から送られた真牡蠣でした。この真牡蠣を種牡蠣として新たに養殖を試みたところ見事に定着し、それ以降、フランスの牡蠣は真牡蠣が主流となったのです。フランスで生牡蠣をお腹いっぱい楽しめるのは、日本のおかげなのです。
「牡蠣にはシャブリ」を色々試して思ったのは、ふくよかな高級シャブリよりも、キリリッと酸が尖っているくらいの方が生牡蠣には合うということ。レモンを絞るが如く、シャブリを合わせるといった感じでしょうか?あくまでも私見ですが。
2023年5月から、「定期ワインコース」のお客様にお届けする冊子「エフスク」にコラムを連載しています。「ワインが好きだな。ワインのことを知りたいな。産地に行ってみたいな。ワインが飲みたーい!」と、皆様に思って頂けるようなワインのある景色をお届けできればと思っています。引続きどうぞよろしくお願い致します。
ライター紹介:新井田 由佳(Yuka Niida)

・J.S.A.認定 ソムリエ
・La Confrerie des Hospitaliers de Pomerol ボルドー ポムロル騎士団称号
大手総合商社在職中にワインに魅了され、退職して渡仏。ブルゴーニュを中心にフランス、イタリアの数多くの生産者を訪問し見聞を広める。知れば知るほど魅了されるワインの世界について、もっと知りたい!が現在進行形で継続中。
-
前の記事

ワインのある景色―9月 (17) 2025.09.01
-
次の記事

ワインのある景色―11月 (19) 2025.11.01