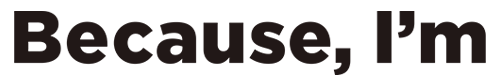【ワインのある物語】『ヘミングウェイ/日はまた昇る』
- 2022.10.03
- ワインのある物語
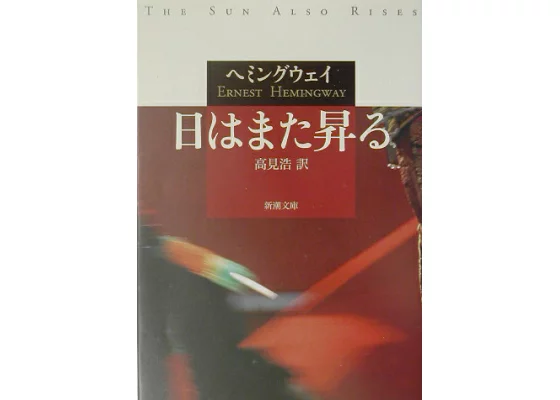
目次
スペインの祝祭

It was like certain dinners I remember from the war. There was much wine, an ignored tension, and a feeling of things coming that you could not prevent happening. Under the wine I lost disgusted feeling and was happy. It seemed they were all such nice people.
それは、あの戦争当時の、ある種の晩餐会に似ていた。その席ではワインがふんだんに振る舞われ、黙殺された緊張があり、不可避の事態が到来する予感が漂っていたものだ。ワインを飲むと、いやな気分も吹っ飛んで、愉快になった。だれもがみんな、素敵な人間に見えてきた。
ヘミングウェイ『日はまた昇る』高見浩 訳
『日はまた昇る』は、1926年に発表されたヘミングウェイ最初の長編小説である。刊行と同時にセンセーションを巻き起こしヘミングウェイを一躍人気作家へと変貌させた。
舞台は発表と同時代の1920年代、つまり第一次世界大戦後のパリ。戦傷で性不能者となった新聞記者のジェイクと、欲望の赴くまま行動したちまち男を夢中にさせる女性ブレット、そして二人を取り巻くブレットの婚約者や新進作家の友人たち。彼らは禁酒法で縛られた祖国アメリカを捨て、パリの自由を謳歌していた。喧嘩、酒三昧、結ばれることのない恋愛。「今日生きること」だけに楽しみを見出す彼らは、さらに生きる証を求めてフィエスタ(祝祭)で沸き立つスペインのパンプローナへと向かう。
冒頭の引用はこの祭りの中でワインに浸るジェイクたちを描いた場面から。ジェイクたちや祭りを楽しむ人々がワインを楽しむ様子は、この作品に何度も登場する。生死を賭けた闘牛が行われる祭りに浸りつつも、ブレットに翻弄された男たちの中には軋轢が生じていく。享楽的な生活の背後にどこか虚無的な喪失感を感じさせる作品である。
ミッドナイト・イン・パリ
第一次大戦後の1920年代、パリは当時の芸術の中心であり、一流の芸術家たちが集っていた。当時のパリにはフランス生まれはもちろんのこと、例えばピカソやダリなどのように他のヨーロッパの国からやってきた者も多かったが、アメリカからやってきた者も多かった。これは第一次大戦が大きく寄与している。
戦場となったヨーロッパでは生産設備などが破壊され、経済が壊滅状態に陥っていた。そのころヨーロッパに代わって超大国への道を歩み出したのが、戦争の傷が浅かったアメリカである。ドルはどんどん強くなり、ドルを持つアメリカ人は、お金持ちでなくてもヨーロッパでで暮らす余裕が出てきたのだ。たとえば、20世紀文学の母とも称されるガートルード・スタイン、『グレート・ギャッツビー』で有名なF・スコット・フィッツジェラルド、そしてヘミングウェイもこの時代のパリに住んでいたアメリカ人である。
(ウディ・アレンの映画『ミッドナイト・イン・パリ』を見ると、わかりやすくこの時代の雰囲気を楽しむことができる。ちなみに、ここに挙げた人物たちは全て映画に登場している。)
さらに当時のアメリカで成立していた禁酒法も寄与した。禁酒法の成立した祖国は窮屈である。彼らは創作活動に勤しみながらも、夜のパリで酒や色恋沙汰といった享楽に身を任せ、堕落した生活を送っていたのである。この時代のパリに若い時代を過ごしたヘミングウェイが、自分と同じパリのアメリカ人を描いたのが『日はまた昇る』なのだ。
ロスト・ジェネレーション
「あなたたちはみんな、自堕落な世代(ロスト・ジェネレーション)なのよね」
この作品の冒頭には、上記のガードルード・スタインの言葉が引用されている。彼女もアメリカからパリへとやってきた、ヘミングウェイの先輩作家であり、創作上の師の一人であった。彼女とのやりとりは晩年に刊行されたヘミングウェイによる青春回想録、『移動祝祭日』に詳しく書かれている。
「あなたたちがそれなのよね。みんなそうなんだわ、あなたたちは」ミス・スタインは言った。「こんどの戦争に従軍したあなたたち若者はね。あなたたちはみんな自堕落な世代(ロスト・ジェネレーション)なのよ」
「そうですかね?」私は訊いた。
「ええ、そうじゃないの」彼女は言いつのった。「あなたたちは何に対しても敬意を持ち合わせていない。お酒を飲めば死ぬほど酔っ払うし……」
ヘミングウェイ『移動祝祭日』高見浩 訳
ヘミングウェイはその後の文章で「人を自堕落な世代と呼ぶなんて何様のつもりなんだ」、「だいたい、どんな世代にも自堕落な部分はあるのだ」などと反発している。幸か不幸かこの”a lost generation”という言葉は、『日はまた昇る』が世に出て大成功を収めた際に「自堕落な世代」ではなく、「迷い子の世代」のような意味で人々に受け取られ、第一次大戦後に世に出たアメリカの作家たちを一括する便利な文学的キャッチフレーズとして定着することとなる。
そのような、自身の世代に対する批判的な言葉をヘミングウェイは冒頭に引用し、その「自堕落な世代」を作品に描いた。
ヘミングウェイ自身は19歳の時に第一次大戦の中でイタリア戦線に赴き、前線に到着後2週間余りで迫撃砲弾を受け、足に重傷を負っている。すぐそばにいた兵士は死に、ヘミングウェイも負傷した同僚を背負って逃げたが、途中で膝を撃たれ、気づいた時には病院のベッドにいたという。『日はまた昇る』の主人公ジェイクも第一次大戦で傷を負ったことで性不能者になっているし、奔放な女友達のブレットも看護師として第一次大戦に参加し、愛する人を赤痢で失っている。この時代の若者は皆、戦争で傷ついたロスト・ジェネレーションなのである。作品の中でロスト・ジェネレーションである登場人物たちが享楽に耽る様は、まるで自身の抱えた傷を癒しているようにも思える。
あえて言えば、傷を抱えた人々は、それでも必死に今を生きようとするからこそ、退廃的な日々を繰り返してしまうのかもしれない。
ヘミングウェイとワイン
葡萄酒ほど文明的なものはないし、これほど最高度に完成された自然物も少い。金で買える純粋に感覚的な事物の中で、おそらくはこれほど広範囲の享受と鑑賞に耐えるものはない。
ヘミングウェイ『午後の死』佐伯彰一/宮本陽吉 訳
ヘミングウェイは大の酒好きとして有名である。一般的にヘミングウェイといえばフローズンダイキリやモヒートなどのイメージが強いが、実はワイン愛好家でもあった。彼の作品ではよくワインが登場しているし、闘牛について解説した『午後の死』という作品の用語解説欄に、ワインという項目を入れているほどである。
スペインへ来る人はシェリーやマラーガのことばかり考えているが、すばらしい、軽い、口当たりのいい赤葡萄酒にはびっくりするだろう。スペインの普通の葡萄酒は、いつもフランスのそれよりもすぐれている。ごまかしや外見を飾ることが少しもないし、値段はフランスの三流どころと同じなのだから。
ヘミングウェイ『午後の死』佐伯彰一/宮本陽吉 訳
そのヘミングウェイがスペインワインの魅力について語っている。フィラディスワインクラブでも訴えているスペインワインのコストパフォーマンスの高さを、ヘミングウェイも主張していたというのが感慨深い。
ヘミングウェイも支持するスペインワインを、ぜひ皆さんもお試しください。そしてもちろんその時は、フィラディスワインクラブでお買い求めください。
2022年10月
<主な参考図書>
ヘミングウェイ『日はまた昇る』高見浩 訳 新潮社
ヘミングウェイ『移動祝祭日』高見浩 訳 新潮社
ヘミングウェイ『午後の死』佐伯彰一/宮本陽吉 訳 三笠書房
*一部「酒」と翻訳されていた箇所を原文が「wine」であることを確認した上で「葡萄酒」に変更している。
クレイグ・ボレス『ヘミングウェイ 美食の冒険』野間けい子 訳 東京アスキー
都甲幸治『100分de名著 ヘミングウェイスペシャル』 NHK出版