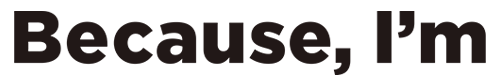【ワインと美術】シベリウスとソクラテスの『饗宴』
- 2022.01.31
- ワインと美術

目次
フィンランドの饗宴
ガッレン=カッレラ『シンポジウム』1894年
個人蔵
男たちが集う。酒を飲み交わす。ひとしきりの議論も済んで、会も終盤というところだろう。一人が酔ってテーブルに伏せっている。明かりの具合や月と背景の色合いから夜であるとも想像できるが、レストランの壁に描かれているだけかもしれない。左側は背景が赤くなっていたり、固い羽のようなものが描かれていたりと、この作品は不思議なところが多い。起きている男たちは、画面左手前を向いている。彼らは何かを見つめているのか。あるいは彼らがこれから対峙することになるフィンランドの運命に、思いを巡らせているところかもしれない。
テーブルの上の酒がワインかどうかはよくわかっていない。むしろプンシュと呼ばれる北欧の伝統的なリキュールであるという説が有力である。ちなみにフィンランドではその緯度からワイン用ブドウの生産が難しく、フィンランド産のワインといえば基本はベリーワインである。ワインを飲んでいないのであれば「ワインと美術」というテーマに反するかと思われるかもしれないが、実は重要なのは彼らが何を飲んでいるかではない。重要なのはこの作品の題名、「シンポジウム」である。
シュンポシオン

シュンポシオンの様子 紀元前475年ごろ
パエストゥム(イタリア カンパーニャ州の遺跡)
シンポジウム。現代では「討論会」と訳されるこの言葉は、ギリシア語「シュンポシオン」を原語とする。意味は文字通り共に(syn)酒を飲むこと(posion)である。古代ギリシアにおいて青年男子自由市民が円形に集ってワインを飲みながら議論を楽しむ文化のことで、この文化は古代ローマへと引き継がれただけでなく、その後のサロン文化にもつながっている。集会で公的に発言するのと異なり、私的空間で酒を共にしながらくつろいで自由に議論を楽しむことが、古代ギリシアの一般的な社会習慣だった。
現代にもつながるこの習慣だが、驚くような点もいくつかある。参加者たちはなんと寝椅子に横になりながらワインを飲み、議論を楽しんだ。そして大皿に入れて右回りで順次回し飲みするのは、あまり酔わないよう水で割ったワインである。当時のワインは現代よりもかなり濃いめでタンニンが多く、そのまま飲むのが難しかった。たとえ上質なワインでも、水を加えずに飲むことは野蛮な行為であった。
古代ギリシアはワイン生産が非常に盛んであった。ギリシアに住む人々の分は当然ながら、歴史上初めて大規模な商業目的での生産が行われたほどである。より多くの収益を得るために彼らは栽培方式や収穫の時期など、現代につながる系統的なワイン生産の方法を確立していった。また生産量が増えると、量よりも質が重視されるようになる。ワインを飲む人々が原産地や生産年を重視し始めるのもこの頃なのである。なかには産地を偽るワインも現れ、それぞれが独自の容器に入れて偽物を製造できないよう対策することも始まった。いつの時代も人間が考えることは大して変わらない。
そんなワイン文化が繁栄した古代ギリシアのシュンポシオンは多様であった。音楽家や踊り手を雇いワインを飲みながら余興を楽しみ、そのまま羽目を外して乱痴気騒ぎに陥ることもあった。かと思えば歌や詩を即興で披露し合う場になったり、哲学や文学に関する公式な討論会になったりもした。そして愛の神エロースをテーマに人々が議論する、この古代ギリシアのシュンポシオンを描いた代表的な作品が、プラトンが著した『シュンポシオン』。邦題にして『饗宴』と呼ばれる作品である。
プラトンの『饗宴』
『饗宴』はかの有名な哲学者ソクラテスが登場する、古代ギリシアのとあるシュンポシオンを題材にした現代まで読み継がれるプラトンの名著である。プラトンはあくまで著者であり、物語には登場しない。
物語の舞台は紀元前416年。アガトンという悲劇詩人を讃える祝勝会における宴会である。当時アテナイで毎年開催されていたワインの神ディオニュソスの祭典では、数日間悲劇と喜劇の新作が市民たちの前で上演され、優勝が競われていた。その年の悲劇コンクールで若手のアガトンが初めて第一等を勝ち取ったのだ。ソフォクレス、エウリピデース、アイスキュロスといった三大悲劇詩人がすでに名声を得ていた時代である。新進気鋭の悲劇詩人アガトンの快挙を祝う席でソクラテスや喜劇詩人アリストファネスといった錚々たるメンバーが集まり、シュンポシオンが始まった。
当時のギリシアは非常に混沌としていた。
紀元前5世紀の初めに行われたペルシアとの戦争には、アテナイやスパルタなどギリシア全体が一丸となって勝利。その後アテナイではペリクレスが実質的な政権を握り、後世においてギリシアの民主政が最もよく機能していたとされている全盛を迎えた。しかし、ペリクレスが拡張政策からスパルタに対して起こしたペロポネソス戦争が始まると、戦況は泥沼化する。10年ほど経過し長引く戦争に疲れ果てた段階で、ようやく一度休戦協定が結ばれたが、アテナイの政治家アルキビアデスが和平を破り、この『饗宴』の時代には実質的に崩壊していた。ペロポネソス戦争を始めたペリクレスは長引く戦争の中で疫病によって亡くなったとされる。著者のプラトンは戦争が始まった後に生まれており、混沌とした時代しか知らない。ソクラテスは何度もこの戦争に従軍している。
終わりのない混沌。まるでウイルスに悩まされる現代と似ているのだ。それでもアテナイの街は一時的な安息を迎えていた。一度結んだ和平が数年の間機能し、街中はまだ戦争の被害を受けていなかったからである。何よりもアガトンという悲劇における期待の星が現れたことが、人々に明るい話題をもたらした。この『饗宴』に描かれるワインを楽しむ宴会は、まさに刹那的な現実逃避の場でもあったのである。
そんな中でこのシュンポシオンという知的遊戯における討論のテーマになったのは、意外にも愛の神エロースである。エロースはギリシアで信仰されていた愛や欲望を司る神。エロースはローマ神話においてはキューピッドと呼ばれるようになり、翼を生やした子供の姿で描かれるのが一般的だが、古い神話ではおどろおどろしい宇宙原初の力であった。そしてギリシア語においてエロースという言葉は、神だけではなくそのまま「愛」そのものも意味する。つまり愛の神エロースを讃えるという名目で、愛というものの確信に迫っていくのだ。参加者は横になった状態で円形に集い、反時計回りの順番でエロースを讃える演説を即興で行う。ソクラテスが演説を行う順番は最後となった。
フィンランドの混沌
ガッレン=カッレラ『シンポジウム』1894年
個人蔵
これらを踏まえて、いよいよ最初の絵画へと戻ろう。ここは19世紀末のフィンランド、現在の首都であるヘルシンキのレストラン。描かれている男たちは、酒やタバコを片手に人生や芸術について語り合う、「シンポジウム」という芸術家集団のメンバーである。当然古代ギリシアのシュンポシオンを意識しているであろうことは想像に難くない。
一番左に描かれているのは、この絵を描いたガッレン=カッレラ。彼はフィンランドの『国民画家』とまで呼ばれ、慕われる存在である。その右で伏せっているのはフィンランドを代表する作曲家の一人であるオスカル・メリカント。その右はわずか二十代の若さでヘルシンキ・フィルを創設した、作曲家・指揮者のロベルト・カヤヌス。そして一番右が一般的な知名度も高く特に有名なフィンランドの作曲家、ジャン・シベリウスである。若い芸術家たちの退廃的な生活ぶりを生々しく描いたこの絵画は、当時世間の不興を大いに買ったという。実際シンポジウムのメンバーの一人が酔った勢いで、「今、みんなでポメリーのシャンパンを楽しんでいるところです!」という内容の電報をスウェーデンの文豪に送り付けたという、だらしないイタズラの逸話も残っている。
しかしこれもまたプラトンに描かれた饗宴と同様に、ある種の現実逃避だっただろう。当時フィンランドは独立への運動の真っ只中にあった。
豊かな大自然やムーミン、おしゃれなインテリアや福祉が充実した国というイメージでおなじみのフィンランド。実はこのフィンランドという国が独立するのはようやく20世紀に入ってからで、1917年に生じたロシア革命の後まで待たなければならない。それまでは600年近くスウェーデンによって、その後は100年ほどロシアによって統治されていた。この絵画が描かれた19世紀末はドイツ帝国誕生によりロシアの防衛におけるフィンランドの重要度が高まり、フィンランドの自治が厳しく制限されるようになった時代である。ロシア側の圧力が強まるほど、それに抗おうとするフィンランド側のナショナリズムが高まっていく。緊迫した雰囲気に包まれる社会的状況。彼らフィンランドの芸術家たちは、否が応にもこの現実と向き合わねばならなかった。フィンランドが迎えている混沌について真剣に語り合ったのか、それともたわいも無い会話で盛り上がったのか。いずれにせよ酒を飲み交わし語り合う饗宴は、一時の安らぎをもたらしたはずである。
エロースを讃える
「各自が好きなだけ飲むことにして、それ以上強制しないこと。」プラトンに描かれた『饗宴』では参加者の一人である医者のエリュクシマコスがこのように節制を促した上で、参加者が順番に愛の神エロースを讃える演説を話していった。権威ある知者の言説を次から次へと引用しエロースを讃える者。聖なる愛と世俗の愛を司る二人のエロースが存在すると主張する者。エロースは宇宙的な調和を司るとして讃える者など、それぞれが直前の演説を踏まえ、時に批判をしながら、多彩で個性的な論を展開していった。
残るは二人。最後から二番目はこの饗宴の主役、若手の悲劇詩人アガトンである。彼はその表現力をいかんなく発揮し、美辞麗句で彩られた演説を即興で紡いでいく。その様は圧巻である。
この神はわれわれから異質なものを消し去り、馴染み深い固有のものを満たしたまう。宴や踊り、そして犠牲を捧げる祭礼の際に導きの神となって、こうしたみんな一緒の集まりを全て取り仕切りたもう、上品さを生み、野蛮を除きながら。情けをもたらすことを好み、悪意を望まず、かくも慈悲深く善きお方。知者には見るべきもの、神々には褒め称えるべきもの。不運なものには妬みの種、幸運なものには豊かな富。優美さ、上品さ、豪奢、恵み、憧れ、そして渇望の父。善き物事を気遣いたまい、悪しきことは見向きもされぬ。苦労の中、恐れの中、渇望の中、そして言葉の中、その際の舵取り、戦闘員、同志そして最善の護り手。ありとしある神々と人間の品よい飾りにして最美最善の導き手。人は全てこの神に美しい祝歌を歌いながら従うべし、なべての神々と人の思いを熱くさせてエロスの神が歌うその歌に与りながら。
まるで彼自身による祝勝演説ともいうべき様である。しかしこの美しい演説は同時にこの時代を象徴するような、虚栄の印象さえも感じられる。上辺は繁栄して華やかに見えるが、内部には虚無や害悪が蔓延しているというような、空虚な当時の現実そのままである。
ソクラテスの問答
ソクラテスの頭像 紀元1世紀ごろ
パリ、ルーヴル美術館
ついにソクラテスが話す番を迎える。ソクラテスはまずそれまでの参加者の演説に疑問を呈した。賞賛するということは決して美辞麗句を並べたてるということではなく、対象についての真実を語ることでは無いかと言うのだ。その上でソクラテスはアガトンに対して質問を重ねる。これこそがソクラテスの真骨頂である。
「兄弟がまさに兄弟であるそのこと自身とは、何かの兄弟であることなのか。そうでは無いのか。」
「何かの兄弟であることです。」
「ではエロース(愛)については、何のエロースでも無いのか。それとも何らかのもののエロースであるのか。」
「何らかのもののエロースです。」
「ではエロースはその何らかのものを欲求するだろうか。それともしないのか。」
「欲求します。」
「欲求し恋しているそのものを持っていて、その上で欲求し恋したりしているのであろうか。それとも持っていなくてか。」
「持っていなくて、ということがもっともらしいですね。」
このようにしてソクラテスは、問答によってエロースという神の正体を暴いていく。愛し求めるということはその対象を保持していないことを意味し、さらに愛する対象には醜いものがあるはずがなく、美があるはずである。そうだとすればエロースという神は美を欠いていることになるのでは無いか。そして善いものは美しいものであるからして、エロースは善いものさえも欠いているとまで提起する。まるで知者とされる人物を問答することでその無知を悟らせるように、散々それまでの参加者によって讃えられてきたエロースの欠点を指摘したのだ。それはまたエロースという存在が、絶対的な存在であるはずの神でないということまで意味する。
場は凍りついてしまった。当然である。アガトンの祝勝会であるにもかかわらず、ソクラテスが一切遠慮せず、会の主役をやりこめてしまったからである。
画家とシベリウス
ガッレン=カッレラ『レンミンカイネンの母』1897年
ヘルシンキ、アテネウム美術館
『シンポジウム』という絵画を描いたカッレラと、そこに描かれたフィンランドを代表する作曲家であるシベリウスにはいくつもの共通点がある。スウェーデン語系フィンランド人というマイノリティとしての境遇や、同時代の混沌としたフィンランドで芸術活動を行なったこと。そして何より、フィンランドの「国民文学」とされる抒情詩『カレワラ』を題材とした作品を生み出していることである。
『カレワラ』は19世紀の初め、フィンランド各地に分散していた民族的叙事詩をまとめたものである。出版当初は素朴な地域文学であったが、スウェーデン語やフランス語など続々と他の言語版が刊行される中で海外での評価が高まり、19世紀後半にはフィンランド民族文化を象徴する存在になっていた。この『カレワラ』はフィンランドの芸術全般に大きな影響を与えるようになる。フィンランドのナショナリズムの機運が高まる中で、芸術家たちはフィンランドのルーツをこの作品に見出そうとしたのだ。
カッレラもシベリウスも、『クッレルヴォ』や『レンミンカイネン』といった『カレワラ』の中に描かれた物語を題材に絵画/音楽を生み出している。彼らはフィンランド独立に向けた運動に、文化的に加担することとなった。
ガッレン=カッレラ『クッレルヴォの呪い』1899年
ヘルシンキ、アテネウム美術館
創作
アガトンをやり込めたソクラテスは、このエロースが美しさを欠いた存在であるという主張は以前に教えを受けたディオティマという女性からの請け売りだと話す。彼女は不思議な存在で、ソクラテスは彼女を昔アテナイで疫病が発生するのを十年間遅らせた人物として紹介する。そして以前に彼女と交わした問答を饗宴の参加者に語り聞かせた。
ディオティマ曰く、エロースは神ではなく神と人間の中間の存在であるという。神という完全な存在であるなら欠乏はなく、美や善に対する欠乏を満たそうとする愛は生まれない。エロースは知恵と無知の中間にいて、知恵を愛し求める存在である。つまりエロースとは知を愛する=フィロソフィア=哲学をする存在なのである。
さらにディオティマはいう。エロース(愛)とは善いものが常に自分にあることの愛求であり、これは万人に共通する望みであると。いつの間にかエロースは存在を意味するのではなく、誰しもが抱く“愛”そのものを意味するようになっている。そしてディオティマは強烈な主張をする。
「(エロースは)美の中で出産し生むことの愛求です」
出産とは決して人間の子を産むことだけを意味するのではなく、創作全般である。例えば法律、芸術作品など、善いものが常にある=不死となることを目指して生み出すことこそが、エロース(愛)の行為としての帰結であるとディオティマは言う。エロース(愛)は、善や美という普遍的な知が不足していることを自覚し、永遠の善や美をもたらすために創作しようとすることにつながるのだ。
『フィンランディア』の創作
作曲家シベリウスは現代の人々をも魅了する普遍的な音楽作品を数多く残した。中でも最も有名なのが『フィンランディア』という作品である。
ロシア側の圧力がますます高まり、それに伴い激しくなるフィンランド独立への趨勢にシベリウスは翻弄されていた。例えば初の交響曲である交響曲第一番を披露したコンサートは大成功を収めたが、聴衆が最も熱狂したのは交響曲ではなく『アテネ人の歌』という愛国的合唱曲だった。もはやシベリウスの作品は、フィンランドのナショナリズムと無縁でいることはできなかった。
そんな中、1900年に行われるパリ万博にヘルシンキ・フィルの派遣が検討されているという知らせがシベリウスのもとに飛び込んでくる。これはフィンランドの存在や自分達の音楽を国際社会にアピールする絶好の機会であった。加えて、なんとシベリウスに一通の匿名での手紙が届く。その内容はこうである。「貴殿は、ヘルシンキ・フィルのパリ万博遠征公演を飾る序曲のような作品を作られたらどうでしょう。すべてを突き抜けたその曲は、そう、『フィンランディア』と名付けられるべきです。」この匿名の手紙に強く心を動かされたシベリウスは、一大決心をして『フィンランディア』というロシア側からすれば極めて挑戦的なタイトルの作品制作に取り組むのである。
結局遠征公演中はロシア側の検閲を逃れるために一時的に『祖国』という名前に変更されたが、この曲をはじめシベリウスの作品がいくつも演奏され、パリだけでなく10以上の各国都市を回った遠征公演は大成功を収めた。この時にヘルシンキ・フィルの指揮を担当したのは、『シンポジウム』の絵画にも描かれていたカヤヌスである。この遠征公演を機にシベリウスの国際的な評価は一気に高まった。
国際的な評価が高まった後もあくまで祖国フィンランドを拠点として活動したシベリウス。独立への過激な抗争、独立後にはフィンランド人同士の内戦までも勃発する。第二次大戦下ではフィンランドはソ連と再び戦争をすることになった。これらの争いで非常に多くのフィンランド人が犠牲になっている。シベリウスが1957年に91歳で亡くなった際、その死亡告知には妻アイノの意向で、「音楽は悲しみから生まれるものです」という言葉が刻まれていた。
撮影者不明 ジャン・シベリウス
1950年代ごろ
アルキビアデス乱入
アンゼルム・フォイエルバッハ『饗宴』1874年
旧国立美術館 ベルリン
それは突然の出来事であった。ソクラテスがディオティマから伝え聞いたことを話し終えると突然門の扉が叩かれて、酔っ払いの大声が響いた。笛吹きの少女とお供を何人か従え、ひどく酔っ払ったアルキビアデスが現れたのである。饗宴を楽しんでいた参加者たちは、現実へと引き戻されたことだろう。なぜならこのアルキビアデスこそが、アテナイを破滅へと導いていく張本人であるからである。
アルキビアデスはソクラテスの弟子であり、またソクラテスを愛していたともされる。当時のギリシアにおいて、年長の男性と青年の愛情関係は社会教育の一環としてよくあることであった。アルキビアデスは超のつくほどの美男子だったといわれる。それも理由の一つか、彼はアテナイの人々から熱狂を持って迎えられた政治家であった。長引く戦争による閉塞感に悩まされた当時のアテナイ。アルキビアデスはせっかく実現した和平をぶち壊し、再び領土拡張へ進んでいく。シチリア島を占領してスパルタや全ギリシアを支配下におこうという無謀な遠征が彼によって実行されるのがこの饗宴の翌年である。そんな無謀な計画に、アテナイの人々は熱狂してしまうことになるのだ。
そんなアルキビアデスは饗宴に乱入し、他の参加者と同様にエロースを讃える演説をすることになるかと思えば、そうはならない。医師エリュクシマコスの提案により、なんとソクラテスを讃える演説をするのだ。アルキビアデスは酔った勢いもあってか、熱を持ってソクラテスを讃える。これまでのソクラテスとの思い出を語りながら、ソクラテスへの溢れ出る愛情を表現する。しかし演説を読むとわかるが、ソクラテスがアルキビアデスを愛していたのかどうかは定かではないのである。ソクラテスを讃える演説が終わり、別の酔っ払いが大勢入ってきて騒ぎになり、そのまま自然とこの饗宴は終わりを迎える。
アルキビアデスが計画し、この翌年に始まった無謀なシチリア遠征は儚くも失敗に終わり、アテナイ軍は全滅する。その後の抵抗むなしく、紀元前404年にアテナイが降伏してスパルタ勢とのペロポネソス戦争は終わりを迎えた。この年にアルキビアデスは暗殺されている。
敗戦後、アテナイにはソクラテスの弟子であった人物を中心とした三十人独裁の軍事政権が誕生するが、千人以上の市民虐殺という恐怖政治が行われ、混乱ののちに民主制が復活。人々はソクラテスを国家に危機をもたらした遠因と考え、よく知られているようにソクラテスは裁判で死刑判決を受けた。そこからさらに20年ほどが過ぎ、『饗宴』がプラトンによって執筆された。
ソクラテス自身は一つの著作も残していない。ソクラテスという存在が永遠となり現代の人々をも惹きつけてやまないのは、プラトンをはじめとした弟子たちによる創作の成果なのである。
ジャック=ルイ・ダヴィド『ソクラテスの死』1787年
ニューヨーク、メトロポリタン美術館
女性の不在:あと書きにかえて
『饗宴』における議論の参加者はすべて男性である。物語で名前が出てくる女性は、ソクラテスにエロースの何たるかを教えたディオティマのみである。
財産権を保障され宴会にも同席し、社会生活も満喫できた古代ローマの女性たちと異なり、古代ギリシアの女性は不自由であった。既婚未婚を問わず、一定の階級以上の夫か父をもつ女性は、祝祭日に行われるのが恒例の神殿までの祭列に加わる以外は、外出の機会すら与えられないのである。必需品の買い物は奴隷が行うか、商人を家に来させる。街に出るのは労働者階級に属する女性たちのみである。家では機織り機で織物をするか、子育てや家事をこなし、夫や父の帰りを待つばかり。シュンポシオンが家で開かれたとしても、夫人は挨拶に出ることすら許されなかった。シュンポシオンに参加できる女性は歌や楽器の演奏、踊りを披露する他国で生まれた娼婦のような存在だけであった。
プラトンが『饗宴』において、愛について語らせる存在をディオティマという女性にしたのは、敢えてのことなのかもしれない。プラトンが後に開いた学園アカデメイアには女性の学徒がいたことが伝わっている。それどころかアカデメイアは異国人でも女性でも年齢も問わず、授業料さえ払わずに誰でも入学できた。そして現代の学校で見られるような講義形式の授業は行われず、多様な人々が集まってテーマを議論するという形式であった。この形式が現代のいわゆるシンポジウムにもつながっている。
この混沌とした現代において、誰しもが参加できる饗宴が、気兼ねなく開催できるようになることを待ち望む。
2022年1月
篠原 魁太
*このコラムにおいての『饗宴』は大胆に抜粋されております。興味を持った方はぜひ原作をお読みください。
<主な参考図書>
プラトン『饗宴: 訳と詳解』山本 巍訳、東京大学出版会
*饗宴の和訳はすべて上記に依拠する。
納富信留『哲学の誕生: ソクラテスとは何者か』筑摩書房
デイヴィッド・M. ハルプリン『同性愛の百年間―ギリシア的愛について』石塚 浩司訳、法政大学出版局
塩野七生『ギリシア人の物語II 民主政の成熟と崩壊』新潮社
トム・スタンデージ『歴史を変えた6つの飲物 ビール、ワイン、蒸留酒、コーヒー、茶、コーラが語る もうひとつの世界史』新井 崇嗣訳、楽工社
内藤道雄『ワインという名のヨーロッパ―ぶどう酒の文化史』八坂書房
納富信留『プラトン哲学への旅 エロースとは何者か』NHK出版
石野 裕子『物語 フィンランドの歴史 – 北欧先進国「バルト海の乙女」の800年』中央公論新社
加藤浩子『音楽で楽しむ名画』平凡社
倉林 靖『音楽と絵画〈下〉マーラーとクリムト、民族楽派から20世紀まで 』芸術現代社
神部智『シベリウス (作曲家 人と作品)』音楽之友社
神部智『シベリウスの交響詩とその時代 神話と音楽をめぐる作曲家の冒険』音楽之友社
松原千振『ジャン・シベリウス 交響曲でたどる生涯』アルテスパブリッシング
森瀬繚『いちばん詳しい「北欧神話」がわかる事典 オーディン、フェンリルからカレワラまで』SBクリエイティブ
リョンロット編『カレワラ』小泉保訳、岩波書店
-
前の記事

【ワインと美術】パリ万博:ボルドー格付けとジャポニスム 2021.09.27
-
次の記事

【ワインと美術:短編】特別展『ポンペイ』とワイン 2022.02.21